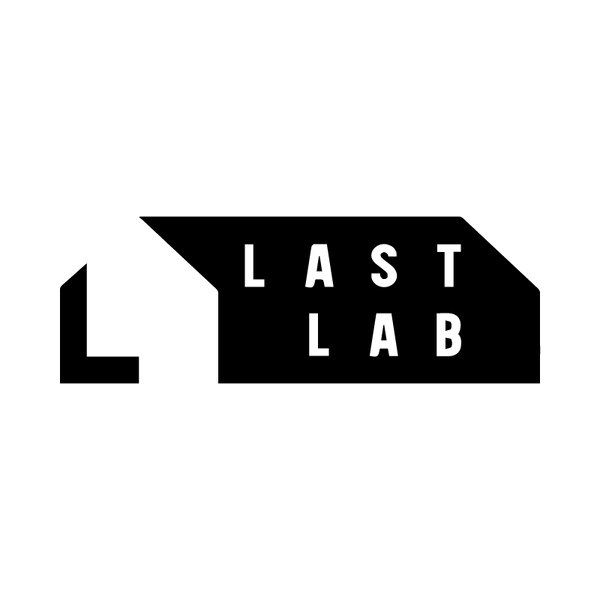「せっかく思い切ってJMウエストンのローファーを買ったのに、履いてみたら思ったよりきつい…」
そんな悩みを感じている方は、実は少なくありません。特に#180 シグニチャーローファーを初めて履いた方の多くが、「これ本当に自分のサイズ?」と不安になるほどのフィット感に戸惑うものです。
でも、その“きつさ”こそが、JMウエストンらしさでもあります。
JMウエストンは1891年、フランス中部リモージュで創業した老舗靴ブランドです。フランス国内では“紳士靴の頂点”とも称され、伝統的なグッドイヤーウェルト製法による堅牢な作りと、計算されたシルエットが特徴。かつてはフランス軍士官学校やエリート層の正装靴としても愛用され、いまなお職人による一貫製造が守られています。
そんな背景から、JMウエストンの靴は「履き始めから快適」というタイプではありません。むしろ、最初は革が硬く、幅も狭め。足入れ時に「修行の始まり」と感じるほどきついことも。しかし、数週間〜数ヶ月の履き慣らし(エイジング)を経て、革が柔らかくなり、持ち主の足形にぴたりと馴染む。まさに“一生もの”と呼ばれる理由はそこにあります。
とはいえ、高級靴だけに「サイズ選びを間違えたかも」「交換すべき?」と不安になるのも当然です。本記事では、そんな悩みに寄り添いながら、JMウエストンのローファーがきついと感じる理由や、モデルごとのサイズ感の違い、馴染ませ方、そして失敗しないサイズ選びのコツを丁寧に解説します。
さらに、渋谷にある中古革靴専門店「ラストラボ」も少しご紹介。こちらでは、すでに履き慣らされたJMウエストンの中古ローファーを数多く扱っており、「新品はきつすぎて不安」という方にもおすすめです。過剰なPRではなく、“自然な選択肢のひとつ”として参考にしてみてください。
JMウエストンのローファーが「きつい」と感じる理由とは
JMウエストンの特徴と作りの堅牢さ
JMウエストンのローファーが「きつい」と言われる最大の理由は、その設計思想と製法にあります。
同ブランドの靴は、創業当初からフランスの伝統的な職人技によって作られ続けており、“長く履いて足に馴染ませる”ことを前提に設計されています。
まず注目したいのが「幅(ウィズ)」です。JMウエストンの木型は全体的に幅狭(はばせま)で甲が低め。日本人の足型(甲高・幅広傾向)とは真逆の作りです。そのため、同じサイズ表記でも国産ブランドや英国靴よりタイトに感じることが多いのです。
さらに、JMウエストンのローファーには、上質で厚みのあるレザーが使われています。特に代表作の「#180 シグニチャーローファー」では、フレンチカーフと呼ばれる硬質な革を採用。新品時はまるで“板”のように感じるほど硬く、足を包み込むような柔らかさが出るまでに時間がかかります。これが「革硬い」と言われるゆえんです。
また、製法もグッドイヤーウェルト製法という堅牢なつくり。中底とアッパー、アウトソールがしっかり縫い合わせられているため、靴全体の剛性が高く、履き初めの段階では可動域が少ないのです。
その結果、足の動きに対して靴がまだ“追従できていない”状態が生まれ、「きつい」「痛い」と感じる原因になります。
しかし、これこそがウエストンの真骨頂。数週間〜数ヶ月かけて革がほぐれ、足型に沿って沈み込んでいくと、次第に信じられないほどのフィット感が生まれます。まさに「修行靴」と呼ばれる所以ですね。
最初の辛抱を乗り越えた先に、“吸い付くような履き心地”が待っているのがJMウエストンというブランドなのです。
きつさを感じる主なポイント
では、具体的にどの部分で「きつい」と感じやすいのでしょうか。
実際に購入者の声や試着時の経験を踏まえると、以下の4つのポイントが代表的です。
-
履き口(ヒールカップ)の食い込み
履き始めは踵をしっかりホールドする構造のため、後ろ側が強く当たることがあります。これを「カカトが大きい」と感じる人もいますが、実際はヒールの保持力が高い証拠。履き込むうちに革が沈み、自然とフィットしていきます。 -
甲の圧迫感
甲の低い設計のため、足の甲が高めの方は特にきつさを感じやすい部分です。新品時は“突っ張る”ような感覚がありますが、ここがしっかり馴染むと、ローファー特有の“抜けにくいフィット”が完成します。 -
足幅(足囲)のタイトさ
前述の通り、ウィズ展開(D〜Eなど)も細めの設定。特に日本人男性の多くが「E〜EE」幅のため、サイズ選びを誤ると側面の圧迫が強く出ます。試着時には小指や母趾球の部分の当たり具合を必ず確認しましょう。 -
全体的な長さと沈み込みの関係
一見すると「長さが短め」に感じる場合がありますが、履き込むと中底が沈み、実際にはちょうどよいフィットに変わります。新品で“ちょっときつい”くらいがベストサイズというのが、ウエストンの定説です。
こうしたポイントを踏まえると、「きつい」という感覚は、単なるサイズミスではなく、むしろ正しいフィッティングの証であることも多いのです。
ただし、「足がしびれる」「甲が痛くて歩けない」といった症状がある場合は要注意。馴染みの範囲を超えている可能性があるので、サイズ交換や別ラストの検討も視野に入れましょう。
モデルごとのサイズ感と特徴を知ろう
#180 シグニチャーローファーの特徴とサイズ感
JMウエストンといえば、まず思い浮かぶのが「#180 シグニチャーローファー」。ブランドを象徴する定番モデルであり、多くの人が「初ウエストン」として選ぶ一足です。
しかし同時に、「きつい」「履くのが大変」と言われるのも、この#180です。
#180のラスト(木型)は、幅狭で甲が低め。足全体を包み込むような形状で、履き口もタイトに設計されています。新品で試着すると、甲部分が強く押さえつけられるように感じることが多く、初見では「小さいのでは?」と思うほど。しかし、JMウエストンの靴は履き込むことで中底が沈み、革が足の形に沿って馴染んでいくため、**少しきつい状態が“正解のサイズ”**なのです。
特にこのモデルの革は厚く、密度の高いフレンチカーフが使われています。最初はまるでプラスチックのように硬いと感じるかもしれませんが、履き慣らすうちに革の繊維がほぐれ、吸い付くような柔らかさに変化します。
この「履き慣らす(エイジング)」期間こそ、ウエストン愛好家が“修行”と呼ぶ所以。慣れるまでに2〜3週間、あるいは1ヶ月以上かかることも珍しくありません。
また、#180は履き口(ヒールカップ)が深く、踵のホールド感が非常に強いのも特徴です。脱げにくくするための設計ですが、最初は「カカトが当たって痛い」と感じる人も。ここも徐々に革が沈んでいくことで自然にフィットします。
サイズ選びのコツとしては、普段履いている英国靴(例:Church’sやCrockett & Jones)よりハーフサイズからワンサイズ小さめを選ぶケースが多いです。
ただし、足幅が広い方や甲が高い方は、無理せずハーフサイズ上げるのもおすすめです。履き込むことで伸びるのは主に横方向なので、縦のサイズを上げすぎると踵が浮きやすくなります。
つまり、#180は“最初はきつくても我慢して履く”靴。馴染んだときの気持ちよさを知ってしまうと、他のローファーには戻れなくなると言われるほどです。
#641 ゴルフ/#677 シグニチャーと比べた違い
同じJMウエストンでも、#180以外のモデルではサイズ感や履き心地がかなり異なります。
代表的なのが「#641 ゴルフ」と「#677 ハントダービー(シグニチャーダービー)」です。
まず#641 ゴルフは、ウエストンの中ではややカジュアル寄りのラストを採用しており、甲にゆとりがあり、全体的に丸みを帯びた形状です。アウトドアや長時間の歩行にも耐えられるよう設計されているため、#180と比べると履き始めから柔らかさを感じやすいモデルです。
ただし、革質はやはり厚めで、履き慣らすまでは一定の硬さがあります。特にサドル部分(甲の中央)は、最初少し突っ張るように感じることもあります。
一方、#677 シグニチャーダービーは、#180と並ぶウエストンの代表作ですが、こちらは**レースアップ構造(紐付き)**のため、甲の締め付けを調整しやすいのが魅力。ローファーのように“固定されたフィット”ではなく、自分の足に合わせて微調整できるので、最初から比較的快適に履ける方が多いです。
ただし、ラストの形状自体はウエストンらしくやや細め。特に土踏まずの絞り込みが強いため、足の形によっては「アーチが当たる」と感じる場合もあります。
どちらのモデルにも共通するのは、**フランス靴らしい均整の取れたフォルムと、長く履くほどに生まれる艶感(エイジング)**です。
「#180は修行がきつそうで心配」という方には、#641や#677から始めてみるのもおすすめです。
同ブランドでもモデルごとに異なる「ラスト(木型)」
JMウエストンの靴選びで最も重要なのが「ラスト(木型)」です。
ラストとは靴の形を決める“設計図”のようなもので、同じサイズ表記でもラストが違えばフィット感はまるで別物になります。
たとえば、#180に使われている「ローファーラスト」は、全体的にタイトで土踏まずの絞りが強い。一方で、#641や#677のような外羽根モデルでは、よりボリューム感があり、甲周りや幅にも余裕が出ます。
この違いを知らずに「同じサイズで大丈夫だろう」と考えると、想像以上にきつい、または緩いと感じる原因になります。
ウエストンはラスト展開が豊富で、モデルごとに微妙な差があります。
-
#180 ローファー:幅狭、甲低め(履き口タイト)
-
#641 ゴルフ:やや広め、甲ゆとりあり
-
#677 ダービー:中間〜やや細め、紐で調整可能
また、同じモデルでも「ウィズ(幅)」が複数展開されていることも特徴です。例えば、D・E・Fなどのウィズ記号があり、日本ではEが標準的な幅ですが、足幅が広い方はFを選ぶと快適です。
ただし、ウィズを上げると甲も少し高くなるため、試着の際は必ず「足当たり」と「踵の浮き」をセットで確認しましょう。
このように、JMウエストンはラストの設計が緻密だからこそ、履き始めの“きつさ”に悩む方が多い一方で、正しく選べば長年愛用できるフィットが得られます。
「きつい=失敗」と思わず、自分の足に合うラストを理解することが、ウエストンとの付き合い方の第一歩です。
きついローファーを快適にする方法
履き慣らし(エイジング)の基本ステップ
JMウエストンのローファーは、「履き慣らす靴」として語られることが多いモデルです。新品の状態では革がまだ硬く、足の動きに沿わないため、最初のうちはどうしてもきつさや痛みを感じやすいのが特徴です。
しかし、正しい履き慣らし方を意識することで、その硬さは少しずつやわらぎ、最終的に自分だけの完璧なフィットへと変化します。
履き慣らしの基本ステップは以下の通りです。
-
最初の数日は短時間だけ履く
いきなり長時間履くのは避けましょう。最初の1〜2週間は、家の中や通勤の短距離など、1〜2時間ほどの着用がおすすめです。少しずつ足と革を慣らすことで、無理なく馴染ませることができます。 -
厚手の靴下を使うのはNG
「きついから厚い靴下で伸ばそう」と思う方もいますが、これは逆効果。靴が不自然に広がってしまい、理想的なフィットを損なうことがあります。履き慣らしの初期は、通常の薄手ソックスでOKです。 -
革の柔軟性を助ける“休ませる時間”を取る
革靴は履いた後に湿気を含みます。乾燥と湿潤を繰り返すことで少しずつ柔らかくなるため、1日履いたら1〜2日は休ませるのが理想です。履き続けよりも「交互履き」の方が早く馴染みます。 -
シューツリーを入れて形をキープする
履き慣らし中にシワや型崩れが出やすいので、木製のシューツリーを入れて形を整えましょう。革が自然なテンションで保たれ、足に沿う形で馴染みやすくなります。 -
1ヶ月を目安に変化を観察する
毎日少しずつ履いていくと、2〜3週間後には甲や踵の当たりが和らぎ、革が足の形に沿って沈み込み始めます。この段階でようやく「自分の靴になった」と実感できるはずです。
JMウエストンの靴は時間をかけて馴染む設計です。焦らず、ゆっくりと革が動き出すのを待ちましょう。その過程自体が“靴を育てる楽しみ”とも言えます。
ストレッチャーや靴下調整での対処法
どうしても履き始めの段階で「痛くて歩けない」「甲が突っ張る」という場合は、軽いストレッチを検討するのも方法のひとつです。
ただし、強引に伸ばすのは禁物。あくまで「部分的に柔らかくする」程度が理想です。
靴用ストレッチャー(シューズストレッチャー)は、自宅で使える便利なツールです。特に小指や親指の付け根など、当たる部分だけを少し広げたいときに活躍します。使用時は、専用のストレッチスプレーを革の内側に軽く吹きかけてからストレッチャーを差し込み、数時間〜一晩ほど放置。これを数回繰り返すことで、わずかに余裕が生まれます。
また、靴下の厚みでの微調整も有効です。履き始めは薄手のソックスで少しでも足入れを楽にし、革が馴染んできたら普段の厚さに戻すという方法が自然です。
逆に「少し緩くなってきた」と感じたら、厚手の靴下を使うことで一時的にフィット感を戻すこともできます。
注意したいのは、靴修理店などでの“機械的なストレッチ”を安易に依頼しないこと。JMウエストンのような高級靴は、革の厚みや縫製が繊細に計算されており、無理に広げるとシルエットが崩れるリスクがあります。
もし自分で調整に不安がある場合は、経験豊富な専門スタッフに相談するのが安心です。
渋谷の中古革靴専門店「ラストラボ」でも、スタッフがサイズ感や馴染み具合の相談に乗ってくれます(※修理やストレッチ作業自体は行っていません)。中古で“すでに馴染んだ靴”を選ぶというのも、実は非常に現実的な解決策です。新品よりも最初から快適で、履き始めの苦労を減らせるのが魅力です。
サイズが合わない判断基準
最後に、「馴染むまで我慢すべきか」「もうサイズを変えるべきか」を見極めるポイントを紹介します。
これは多くの方が悩む部分ですが、見極めにはいくつかの目安があります。
▶ 履き慣らしで解消できる“きつさ”のサイン
-
歩けるが、足の甲や側面に軽い圧迫を感じる
-
脱げない程度に踵がしっかりホールドされている
-
小指や親指の当たりが「軽く」痛いくらい
この程度であれば、履き慣らすことで解消する可能性が高いです。
▶ サイズ交換を検討すべき“痛み”のサイン
-
甲が極端に当たって血行が悪くなる
-
小指や踵が赤く腫れるほど痛む
-
履いて5〜10分で我慢できない
このような場合は、ラストの形やサイズが根本的に合っていない可能性があります。
また、試着時には「つま先に5〜10mmほどの余裕」があるか、「踵が浮かないか」をチェックしましょう。新品で全く動かせないほど窮屈なら、履き慣らしでも解決は難しい場合があります。
JMウエストンの靴は高価な投資です。焦って我慢し続けるより、早めに販売店に相談してサイズ交換を検討するほうが結果的に満足度は高くなります。
一方、「中古で試す」という手段も有効です。すでに革が馴染んだ靴なら、履き心地を確認しながら自分に合ったサイズ感を見極めやすいでしょう。
サイズ選びで失敗しないためのコツ
H3:足のサイズとウィズ(幅)を正確に知る
JMウエストンの靴を選ぶ上で、まず大切なのは「自分の足のサイズを正確に知ること」です。多くの人が“普段のスニーカーサイズ”を基準に革靴を選びがちですが、それは失敗のもと。
スニーカーと革靴では足の包み方がまったく異なり、革靴の場合は「足長」だけでなく「足幅(足囲)」と「甲の高さ」も重要な要素になります。
ウエストンの靴は特にウィズ(幅)が細めに設定されています。
たとえば日本人の平均的な足幅は「E〜EE」ですが、JMウエストンの標準ウィズは「C〜E」。つまり、日本人の多くが“幅狭”に感じやすい設計なのです。
そのため、購入前には靴屋で足長・足囲をミリ単位で計測し、自分のウィズを把握しておくことを強くおすすめします。
もし自宅で簡易的に測るなら、以下の方法でもおおよそのサイズ感が分かります。
-
紙の上に足を置いて、踵からつま先までを直線で測る(足長)
-
足の一番広い部分(親指の付け根〜小指の付け根)をぐるりと測る(足囲)
-
足囲の数値を靴のサイズ表に当てはめ、ウィズを確認する
こうして自分の「足の傾向」を把握しておくと、ウエストンのどのラストが合いやすいかが見えてきます。
特に幅が広めの方は、標準ウィズではなく「ワイドフィット(Eなど)」を検討するのもおすすめ。反対に足幅が細めの方は、Cウィズが驚くほど心地よく感じるはずです。
購入前に試しておきたいポイント
JMウエストンのローファーを初めて購入するなら、「試着の質」が命です。
店頭で短時間試しただけでは分からない部分も多いため、以下のポイントを意識してチェックしてみてください。
-
靴下は普段履きの厚さで試す
厚手のソックスやナイロンソックスでは感覚が変わります。普段使う靴下で試すのが正確です。 -
時間帯を変えて試着する
人の足は朝より夕方の方がむくんでいます。朝にぴったりだと、午後はきつく感じることも。購入前には午後〜夕方の試着がおすすめです。 -
両足で試すこと
左右の足で大きさや形が違うのはごく普通のこと。必ず両足を履き、立って体重をかけたときの感覚を確かめましょう。 -
つま先の余裕と踵の浮き具合をチェック
目安として、つま先に5〜10mmの空間があり、踵が軽くホールドされている状態が理想です。新品時にわずかにきついくらいが、馴染んだ頃には完璧なサイズ感になります。
もし複数サイズで迷った場合は、販売員に相談するのも有効です。JMウエストンを扱う専門店では、スタッフが“履き慣れ後の伸び”を前提にアドバイスしてくれます。
ただ、試着に慣れていない人は「どれも同じに感じる」と思うかもしれません。そんなときは、実際に履き慣らされた中古靴を試して“馴染んだ後の感覚”を体験するのも良い方法です。
中古革靴という選択肢(ラストラボ紹介)
新品のJMウエストンは、履き慣らしに時間がかかるうえ、値段も決して安くはありません。
そのため、中古で状態の良い一足を探すというのも、とても賢い選択です。
中古革靴の魅力は、すでに前オーナーによって「革が柔らかく馴染んでいる」点です。
最初から足入れがしやすく、“きつさ”をほとんど感じずに履けるケースも多いです。もちろん、ソールの状態や型崩れの有無などは確認が必要ですが、上質な革靴ほど時間を経てもその価値を保ち続けます。
渋谷にある中古革靴専門店 「ラストラボ(LAST LAB)」 では、JMウエストンをはじめとした名門ブランドの中古靴を幅広く取り扱っています。スタッフが1足ずつ丁寧にコンディションをチェックしており、状態の良いウエストンを探すにはぴったりのお店です。
特に#180や#641といった人気モデルも入荷することが多く、「新品の堅さが不安」「サイズ感を確認してから新品を買いたい」という方にもおすすめ。
ラストラボでは修理やストレッチなどの作業は行っていませんが、履き心地やサイズ選びの相談には親身に対応してくれます。
店舗で実際に履いてみれば、自分に合うウィズやラストの感覚が掴みやすく、今後の靴選びにもきっと役立つでしょう。
中古革靴は、決して妥協ではなく“賢い選択”。
新品のウエストンが「きつい」と感じて諦めかけた方も、一度ラストラボで馴染み済みのローファーを体験してみてください。想像以上に快適な履き心地に驚くはずです。
まとめ:きついのは「良い靴の証」?焦らず馴染ませよう
JMウエストンのローファーを初めて履いたとき、多くの人が「え、こんなにきついの?」と驚きます。
しかし、その“きつさ”こそが、ウエストンというブランドの魅力であり、長年愛され続ける理由でもあります。
フランス・リモージュで1891年に生まれたJMウエストンは、職人による伝統的な製法を今も守り続けています。グッドイヤーウェルト製法で作られた靴は、履き始めこそ硬く頑丈ですが、時間をかけて足に馴染んでいくことで、まるで自分の皮膚の一部のようにフィットしてくれる。これほどまでに「育つ靴」は、実はそう多くありません。
特に#180 シグニチャーローファーは、最初の履き心地の厳しさから「修行靴」と呼ばれることもありますが、履き慣らした後の快適さは格別。足に吸い付くようなフィット感と、歩くたびに鳴る軽やかな革の音。そこに到達した瞬間、JMウエストンの真価を実感するはずです。
また、モデルごとに異なるラスト(木型)を理解し、自分の足に合ったウィズを選ぶことも重要です。
足幅や甲の高さは人それぞれ。無理に小さいサイズを我慢して履く必要はありませんが、「少しきつい」からこそ得られる一体感を、恐れずに楽しんでみてください。
どうしても不安な方は、中古のJMウエストンを選ぶのも賢い方法です。渋谷の中古革靴専門店「ラストラボ」では、すでに馴染んだ状態のウエストンを手に取ることができ、サイズ感の目安をつかむのに最適です。修理は行っていませんが、靴選びやフィッティングの相談は丁寧に対応してくれるので、気軽に立ち寄ってみるのもおすすめです。
高級靴は「買って終わり」ではなく、「履いて育てるもの」。
JMウエストンのローファーも、最初の“きつい期間”を経てこそ本当の魅力を発揮します。焦らず、自分のペースで少しずつ馴染ませていけば、数年後には“世界で一番自分に合う靴”になっているはずです。
「きついからダメ」ではなく、「きついからこそ良い靴」。
そんな視点でJMウエストンと向き合えば、履くたびに少しずつ、あなたの足に寄り添う相棒へと育っていくでしょう。